はじめに
「秋の東京芝=瞬発力勝負」。競馬ファンにとってはおなじみのフレーズです。特に天皇賞・秋(東京芝2000m)は「直線ヨーイドン」「切れ味勝負」というイメージが強く、多くの予想記事でも“瞬発力タイプ有利”と語られます。
しかし、果たしてそれは本当に絶対的な法則なのでしょうか?
本稿ではL3(ラスト3ハロン)のラップ分析を切り口に、“瞬発力神話”の実態を整理。さらに天皇賞・秋の過去レースを例に、瞬発力型と持続力型のせめぎ合いを解剖します。
東京芝2000mの特徴
東京競馬場の芝2000mは、スタンド前発走で最初の1コーナーまでの距離が短く、序盤の位置取り争いはシビアです。その後は中盤で落ち着き、直線約525m+ゴール前の急坂が待ち受けるレイアウト。
- スタートから序盤:ポジション争いが激しくなりやすい
- 中盤:ペースが緩んで“溜め”が生まれることが多い
- 終盤:直線L3からのロングスパート戦になりやすい
これが「瞬発力勝負=神話」を生む背景といえるでしょう。
L3ラップで見る“瞬発力”とは?
L3ラップとは
L3=ラスト3ハロン(600〜200m区間)のラップを指します。
- L3が11.5秒以下 → 明確な瞬発力戦
- L3が12秒前後で持続 → スタミナや底力が問われる
- L2(ラスト2F)が極端に速い → “ヨーイドン型”
つまり、L3の推移=レースの質を映す鏡なのです。
東京芝2000mの傾向
過去10年の東京芝2000m重賞を俯瞰すると、
- 直線に入ってからの加速性能(L3→L2の伸び)が勝敗を分けるケースが多い
- ただし、G1クラスではL4(ラスト4ハロン)から速いラップを刻み続ける持続力戦になる年もある
→ 単純な「瞬発力=切れ味」だけでは片づけられないのです。
天皇賞・秋をL3ラップで振り返る
例1:2017年(キタサンブラック)
- 道中スローからのL4ロングスパート
- L3以降も緩まず、持続力勝負に
- 結果:瞬発力型よりスタミナ&粘り強さでキタサンが押し切り
例2:2019年(アーモンドアイ)
- L3=11.6、L2=11.3という明確な加速
- ラスト2Fでのトップスピードが決定打
- 結果:瞬発力神話の典型的証明
例3:2022年(イクイノックス)
- 前半から締まった流れ
- L3=11.7、L2=11.5と速い持続戦
- 結果:高次元の持続力+瞬発力を兼備した馬が勝利
例4:2023年(イクイノックス連覇)
- ペースが上がり切らず直線瞬発戦
- L3=11.3、L2=11.1の鋭い加速
- 結果:瞬発力型+操縦性の高さが完勝要因
神話をどう捉えるべきか
上記の例からわかるのは、
- 瞬発力型が強い年も確かにある
- しかし持続力型が勝つ年もある
- 要は「ペース設計」「道中の仕掛け」で質が変わる
つまり「秋の東京=瞬発力神話」というよりは、
“瞬発力を問われやすいが、持続力が不要になるわけではない”
と表現するのが実態に近いでしょう。
馬券戦略に落とし込むなら
1. 瞬発力型人気馬の“妙味消失”に注意
直線加速が武器の人気馬は過剰に支持されやすい。
→ 道中締まった流れやハイラップ戦では脆さを見せる。
2. 持続力型の“拾いどころ”を探す
ハイペース想定時は、むしろ持続力型に妙味がある。
特に「前走厳しい流れで粘った馬」は狙い目。
3. L3ラップ予測をレース前に描く
- スロー濃厚:瞬発力型◎
- ミドル以上:持続力型浮上
- 馬場状態(稍重〜不良)で瞬発力が削がれる場合も考慮
まとめ
- 秋の東京=瞬発力神話は“部分的に真実”
- 実際の勝敗はL3ラップの質(加速か持続か)で決まる
- 天皇賞・秋はその年ごとに傾向が異なり、瞬発力型と持続力型のバランスを読むことが重要
競馬予想で「東京=瞬発力」と決めつけるのは危険。
L3ラップを軸に“今年の質”を読み解く視点こそ、妙味ある馬券戦略につながるのです。
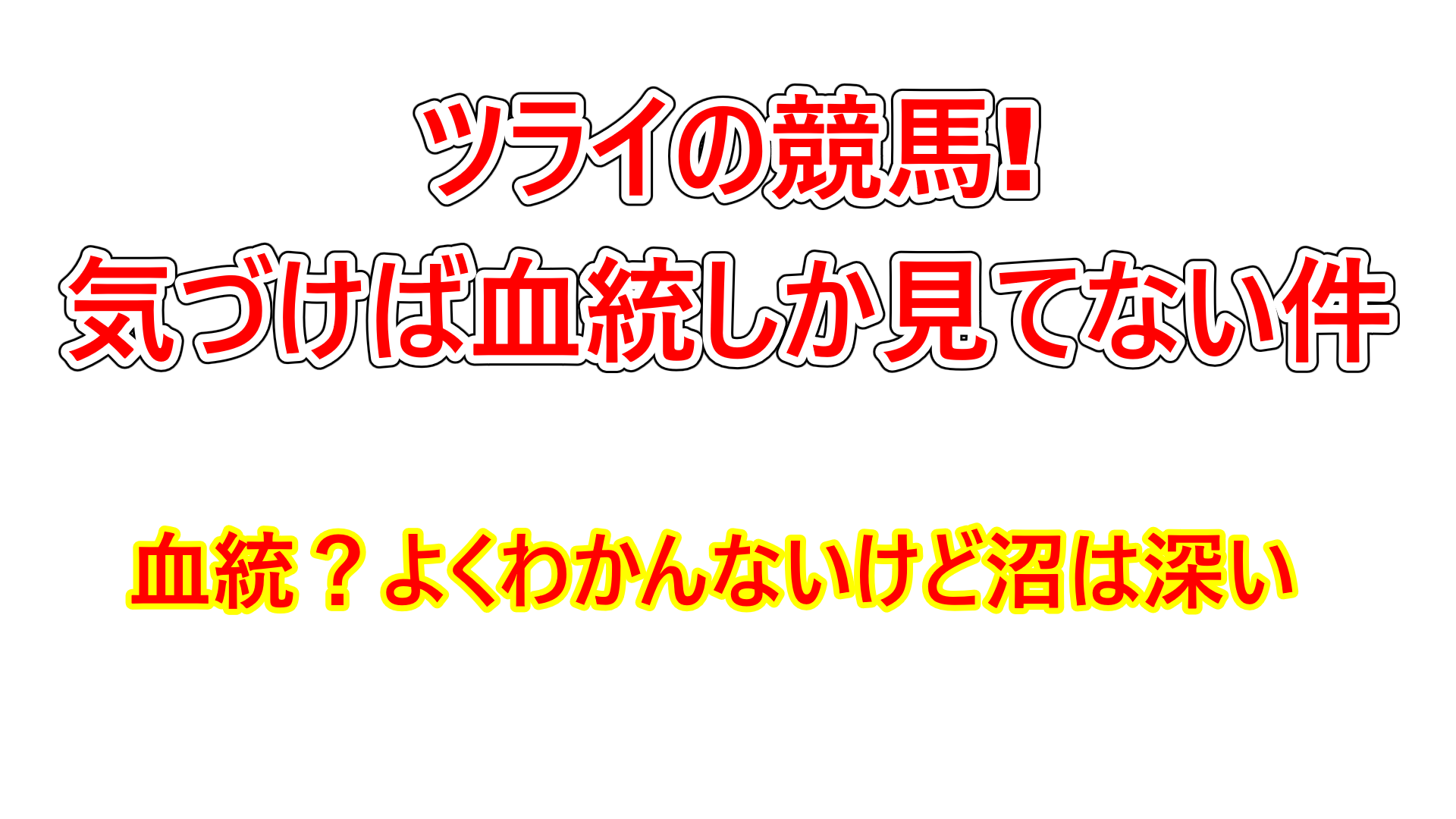

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c41beb7.54b0e9cf.4c41beb8.a3c03bfb/?me_id=1213310&item_id=21673357&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5504%2F9784867105504_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca3c3cc.d7e5577d.4ca3c3cd.a934b7e8/?me_id=1419945&item_id=10001394&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Firodori-ic%2Fcabinet%2Ffolder3%2Fwkbokkusugaisen1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント