天皇賞・秋「過去10年ラップ“型”診断」——瞬発か、持続か、その主導権は誰の脚?
東京芝2000mの天皇賞・秋は「長い直線=切れ味勝負」という固定観念を持たれがちですが、ふたを開けると年ごとにレースの“型”が別物になります。ここ10年(2015〜2024)を、前半5F-後半5Fの配分と終盤の区間推移から整理し、瞬発力(後傾)と持続力(前傾~フラット)のどちらが勝ち筋として優勢だったか、そして今年の見立てにどう落とし込むかを立体的に描きます。
①コースが問うのは「瞬発×地力の掛け算」
スタートは1コーナー手前のポケット。序盤は落ち着きやすい一方で、中盤から11秒台が連続しやすく、直線での瞬発力だけでなくその手前から脚を使い続ける持続耐性も要求されます。加えて外枠はポジションを取りにくく、無駄足=終盤の鈍化に直結。すなわち「切れ味だけでは足りないが、地力だけでも届かない」――複合テストの色合いが濃い舞台です。
②過去10年の“型”の分布と象徴ラップ
2015–2021:後傾=瞬発型が主流
- 2015(1:58.4):+2.8秒の後傾
- 2016(1:59.3):+2.3秒の後傾
- 2017(2:08.3・不良):+0.1秒のほぼフラット(特殊馬場)
- 2018(1:56.8):+2.0秒の後傾
- 2019(1:56.2):+1.8秒だが残り4F=11.3–11.1–11.3–11.9のロンスパ色が強い“複合型”
- 2020(1:57.8):+3.2秒の強後傾
- 2021(1:57.9):+3.1秒の強後傾
2022–2024:持続→フラット→再び瞬発
- 2022(1:57.5):−3.2秒の前傾=超ハイラップの持続戦
- 2023(1:55.2・日本レコード):11秒台の均一進行=フラット寄りの持続(12.4–11.0–11.5–11.4–11.4–11.4–11.4–11.6–11.4–11.7)
- 2024(1:57.3):59.9-57.4(後傾2.5秒)でレース上がり33.7、勝ち馬の上がりは32.5——瞬発力型の象徴
集計:
- 瞬発型(明確な後傾)=7回(2015/16/18/19/20/21/24)
- 持続~フラット型=3回(2017/22/23)
→ 「瞬発優勢」という母集団を持ちながらも、2022–2023に“ラップの質の揺り戻し”が発生。主導権(逃げ・先行)の脚質と隊列によって、同じ東京2000mでも問われる能力がガラッと変わるのが実像です。
③勝ち筋を“型”で定義する
瞬発力型(後傾ラップ)
- 像:前半が緩み→L3~L2で鋭くギアアップ。
- 要件:L3〜L2で10秒台後半〜11.2前後へ加速できる“トップスピードの質”+中団〜好位で脚を温存できる器用さ。
- 典型:2020・2021の強後傾、2024のような33秒台前半のレース上がりに“32秒台”で差す決め手。
持続力型(前傾~フラット)
- 像:中盤以降が11秒台の連打→4~5Fのロングスパート戦。
- 要件:L5~L4でスピードを落とさず巡航できる地力と心肺、先行~中団での止まらない脚。
- 典型:2022の前傾ハイラップ、2023の均一高水準。瞬発の一点突破では足りず、総合的な巡航速度を問われる。
④“型”を決めるスイッチはどこにある?
- 逃げ/先行の質
- 前半から“落とさない”リーダーがいると前傾~フラットへ。
- 逆に前半で息を入れるタイプが主導なら後傾=瞬発型が濃くなる。
- 並びと枠順
- 外から主張が多い並びは入りが速くなりやすい。外枠は位置を取りに行く過程で脚を使い、ロンスパ耐性がないと最後に甘くなる。
- 馬場と風
- 超高速馬場+追い風直線は上がり性能を上振れさせ、瞬発型が決まりやすい。逆に時計の掛かりやすいコンディションは地力の持続を後押し。
- 有力馬の“勝ちパターン”の再現性
- 毎日王冠型で勝ち上がるタイプは後傾◎、大阪杯・札幌記念型の好走実績はロンスパ適性◎と読める。
⑤今年(2025)を占うための4つのチェックリスト
- ① 逃げの巡航像:マイル~2000mでL5~L4を11秒台で踏み続けての粘り込みがある逃げ・先行が複数並ぶか。
- ② 直線加速の“質”:L3=33秒前半~32秒台の絶対速度を持つ馬が主力か、それともL4=45秒台前半でまとめる巡航型が多数か。
- ③ 枠とポジション:外から被されにくい配置を引けた“切れ馬”は後傾で加点、内~中枠で先行確保できる“地力馬”は前傾~フラットで加点。
- ④ 阪神・中山のタフ戦歴:近走で消耗戦を好走している馬はペースが上がった時の下支えになる。逆に瞬発一点型はペースの上振れを待つ立場。
⑥馬券戦略“型合わせ”
想定:後傾=瞬発力型
- 本線:中団前~好位で溜め→L2でもう一段ギアを使える馬
- 相手:中団差しでL2~L1の爆発力が裏付けられているタイプ
- 押さえ:先行してもラスト11秒前半まで詰められる器用型
- 評価軸:近3走に上がりL3=33.5以内/一瞬でトップスピードへ移行できるレースを持つか
想定:前傾~フラット=持続力型
- 本線:先行~好位でL5~L4を落とさない巡航型
- 相手:中団差しでもラップを刻み続けて止まらないタイプ
- 押さえ:枠利+ロンスパ耐性のセットを持つ馬
- 評価軸:高速持続レース/渋った馬場での消耗戦好走の履歴
ポイントは「想定ラップ → 印」の順番で思考を固定すること。
どの馬が流れを作るかを先に決め、それに適合する能力曲線(瞬発 or 持続)を持つ馬に寄せる——これが的中率と回収率の両立に効きます。
⑦まとめ
- 過去10年は瞬発7:持続/フラット3で瞬発優勢。
- ただし2022–2023の連続で分かるように、主導権の質と並びひとつでレースは“切れ比べ”から“地力の押し合い”に一変します。
- 東京2000mは外からロスなく運ぶのが難しいため、位置取りの設計と脚の使いどころを明確に描ける馬を上位評価。
今年もまずはペースの絵を先に描く。そのうえで、瞬発と持続、どちらの“型”に寄せるかを決め、印と券種を最短距離で組み立てるこれが天皇賞・秋の頂上決戦を獲りにいく方法かもです(笑)
関連リンク
・【ウマ娘ファン向け】あの名馬の血は今も生きている!ゲームから入る感動の血統入門
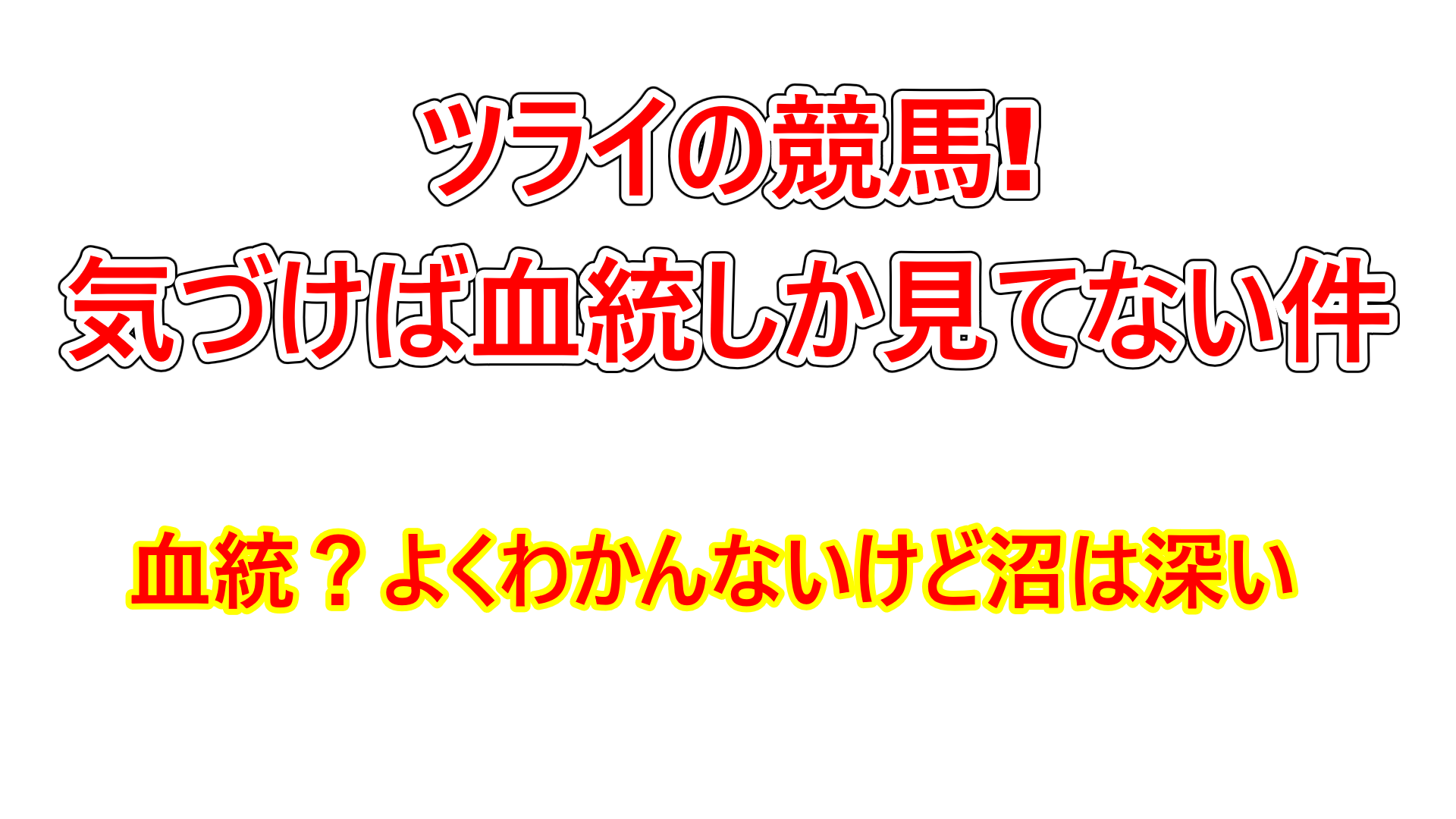

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c9b8148.7afc8fbb.4c9b8149.cf7e578a/?me_id=1349074&item_id=10001429&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff392065-susaki%2Fcabinet%2F06172339%2Fimgrc0104513339.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d66b061.a4829e27.4d66b062.ab115cd5/?me_id=1382521&item_id=10001025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff014028-iwanai%2Fcabinet%2F10753224%2F10753235%2F12261511%2F003-a002sku_c.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
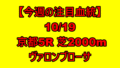

コメント